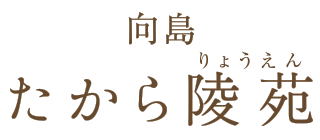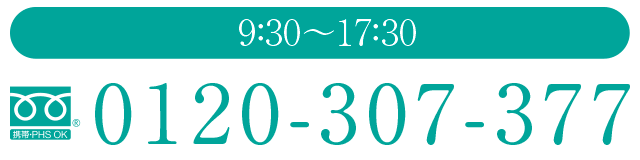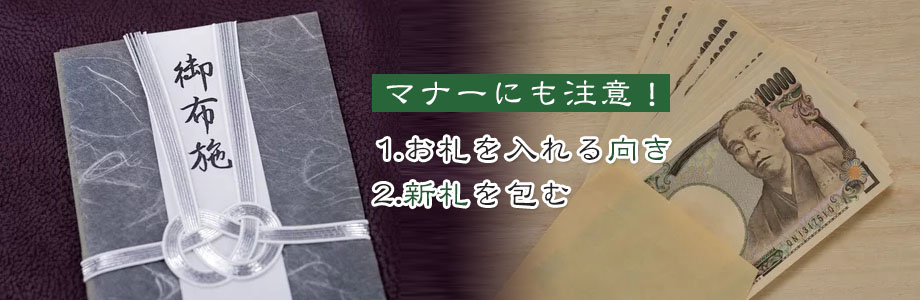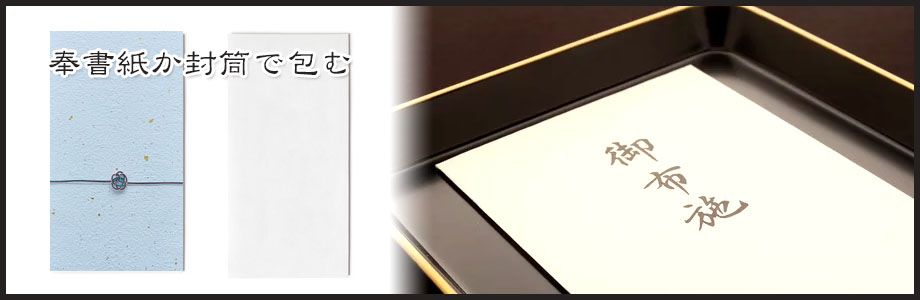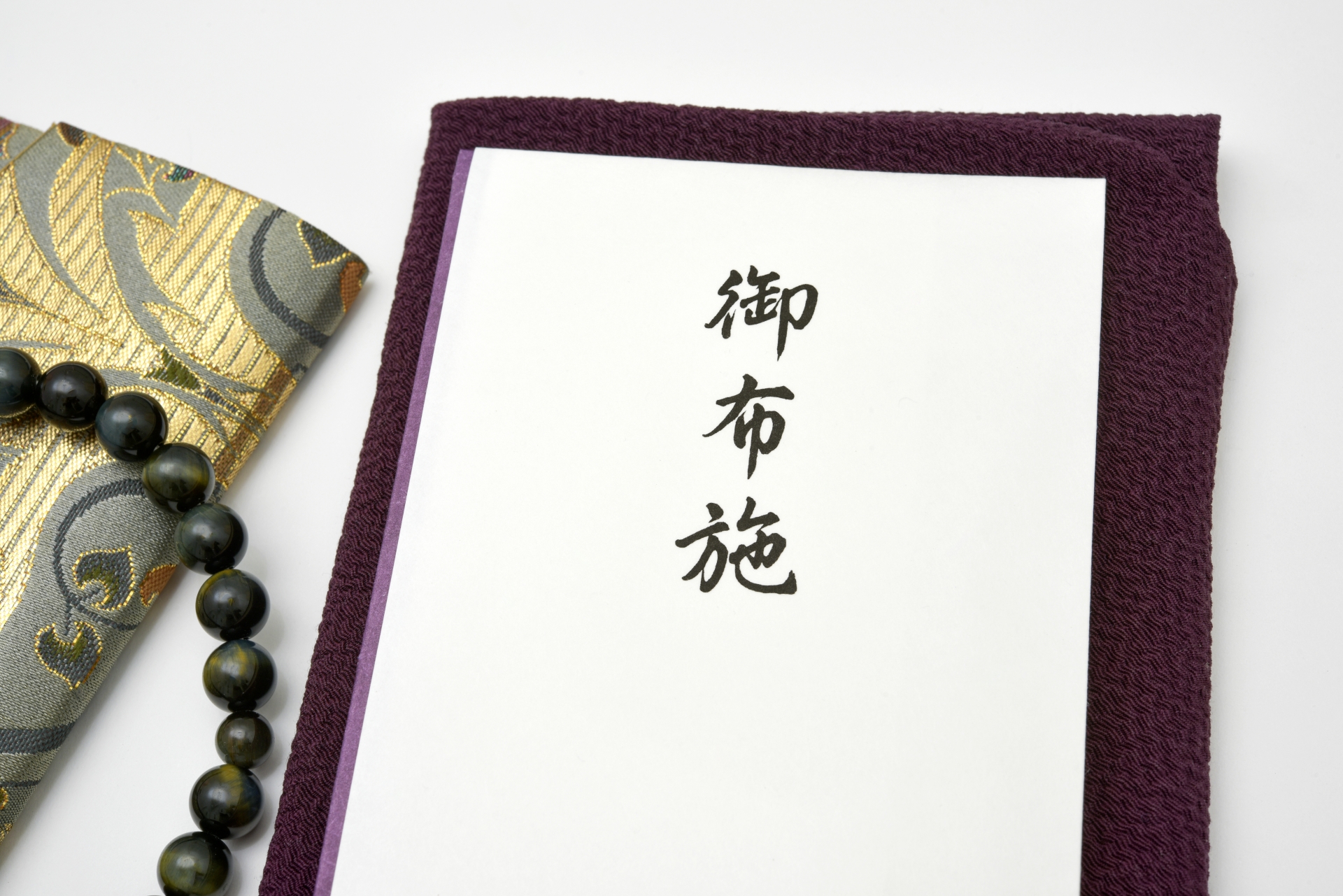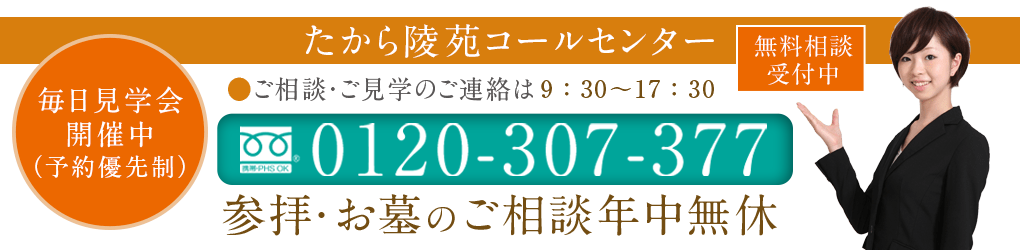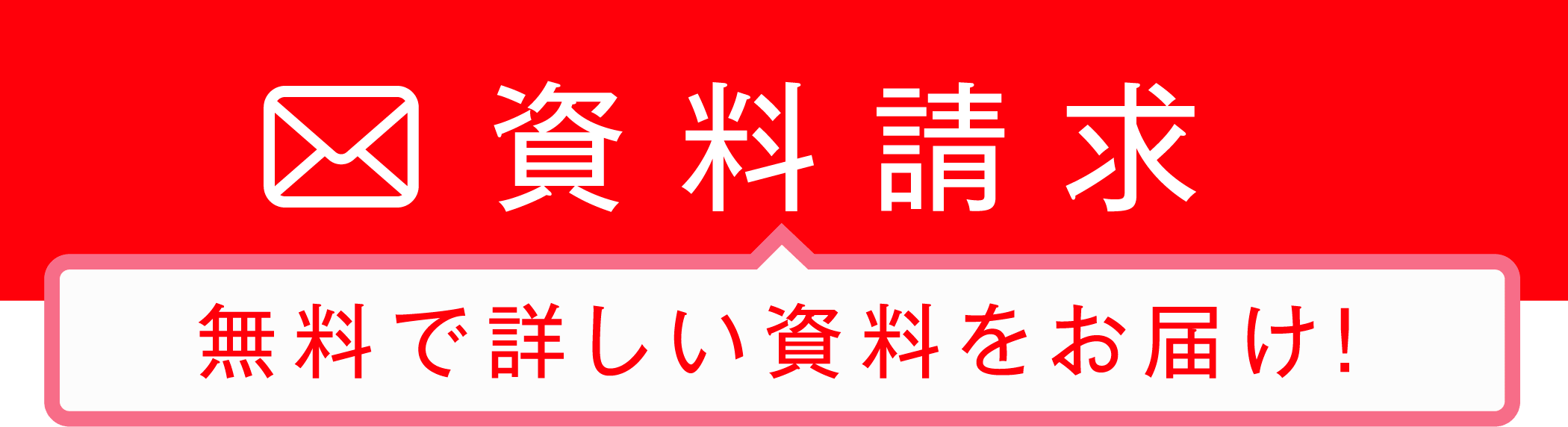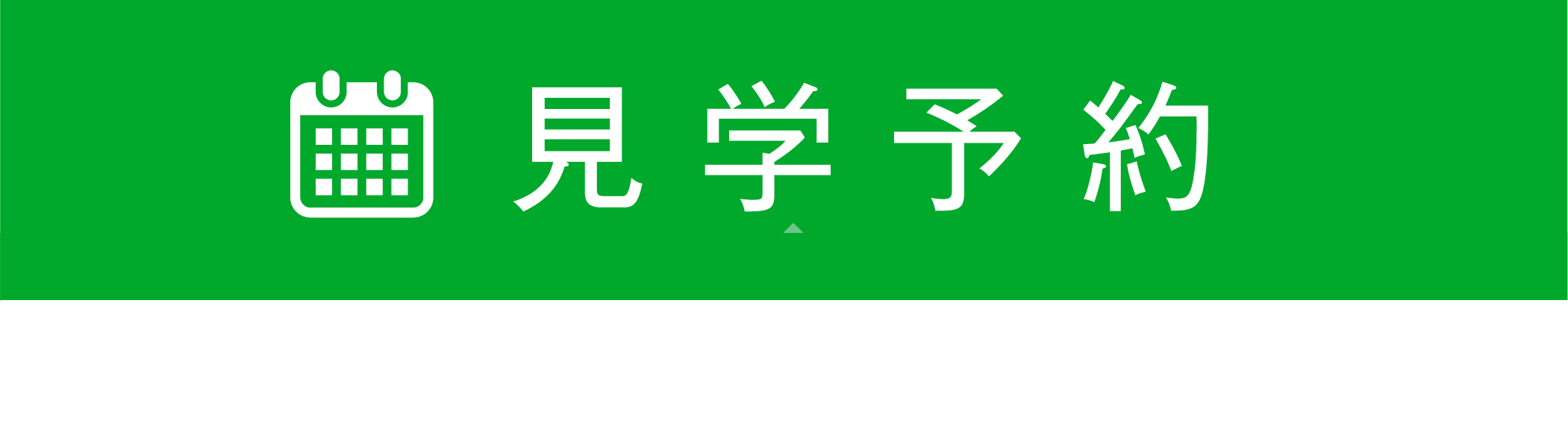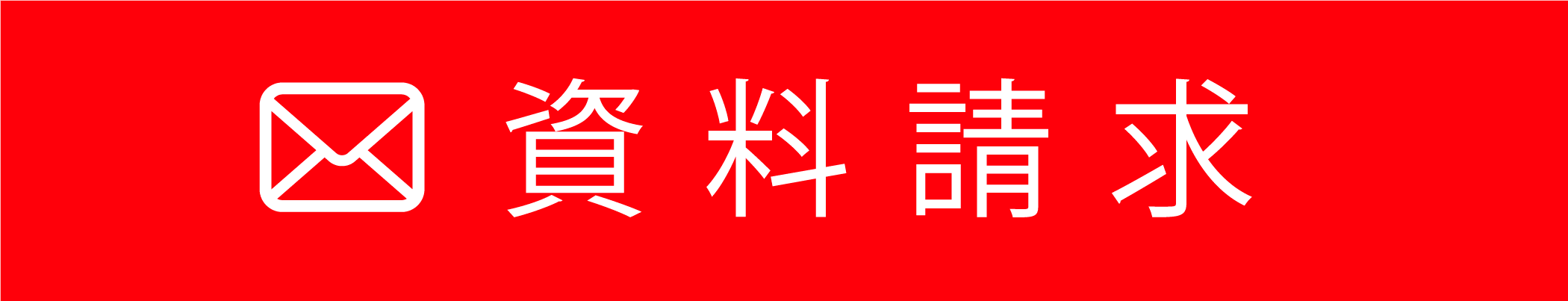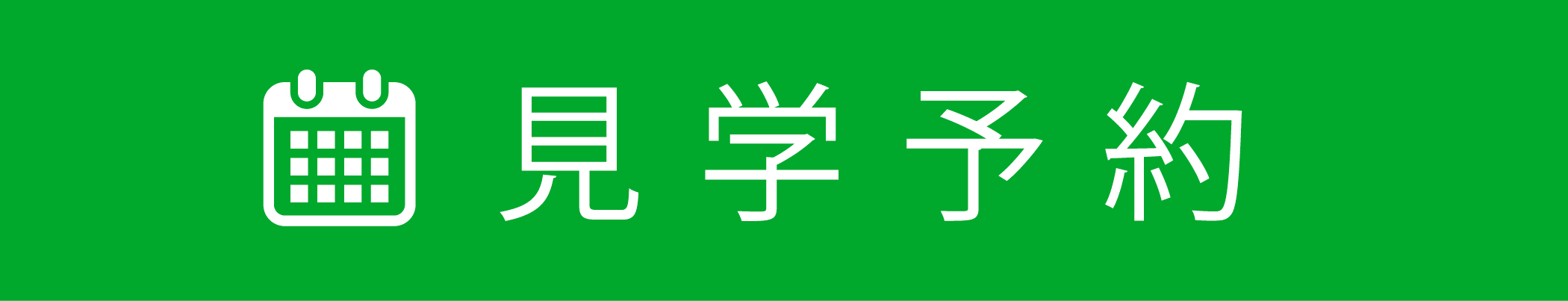永代供養でお布施は必要?書き方や金額の内訳・相場を解説 | 向島たから陵苑


寺院や霊園が代行してお墓を管理する「永代供養」では、永代供養料にお布施が含まれているため、基本的にはお布施を個別で用意する必要がありません。しかし、寺院によっては読経料や戒名料が別途にかかる場合があります。
当記事では、永代供養のお布施の有無や金額相場、お布施の正しい記入方法と包み方を解説します。永代供養を利用したい人やお布施の正しいマナーを知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
永代供養のお布施は必要?
お布施とは、仏教徒が行う六波羅蜜と呼ばれる修行の一環であり、金品のように物質的なものを施す「財施」に当たります。近年では僧侶への謝礼としての意味合いが強まっていますが、正確には寺院のご本尊にお供えする捧げものです。そのため大半の寺院では、いただいたお布施の多くはご本尊をお守りするための建物や布教活動のための費用に使います。
永代供養は寺院の墓地や霊園にお墓を建てず、共用の永代供養墓や納骨堂に遺骨を合祀して故人の供養・管理を依頼する、最近人気が高まっている埋葬方法です。いわゆる「檀家」と「菩提寺」の関係にはならないことが多いため、お布施の必要性を疑問に感じる人もいるでしょう。
永代供養の場合、永代供養料に納骨法要時のお布施が含まれており、個別に用意する必要のないケースが一般的です。ただし葬儀や一周忌、三回忌などの法要に伴うお布施は含まれていません。
寺院によってもお布施への考え方は異なるため、事前に確認しておきましょう。
永代供養のお布施の内訳と金額相場
多くの場合、永代供養ではお布施を含んだ金額が提示されますが、寺院によっては別途下記のお布施が必要です。
| 読経料 | |
|---|---|
| 通夜や葬儀、火葬場で僧侶にお経を読んでもらうときに渡すお布施です。宗派によっては信徒の収入に対して1~2割程度と定める場合もあります。 | |
| 金額相場 | 15万円以上 |
| お車代 | |
|---|---|
| 僧侶に自宅や葬儀場まで出向いてもらうときに渡すお布施です。寺院から動かない場合は必要ありません。 | |
| 金額相場 | 1万円程度 |
| 戒名料 | |
|---|---|
| 故人に戒名を付ける際に渡すお布施です。宗派や戒名のランクによって金額の相場は異なります。 | |
| 金額相場 | 数万円~100万円以上 |
| 納骨法要 | |
|---|---|
| 納骨時に法要を執り行うときに渡すお布施です。永代供養料に含まれている場合は必要ありません。 | |
| 金額相場 | 3万円程度 |
| 年忌法要 |
|---|
| 初七日やお盆、一周忌などの年忌法要を執り行う際に渡すお布施です。永代供養料には含まれていないため、都度渡す必要があります。 |
年忌法要のスケジュールと、お布施の金額相場の目安は下記の通りです。
| 初七日 | 3万円~5万円 |
|---|---|
| 四十九日 | 3万円~5万円 |
| 納骨 | 3万円 四十九日と一緒に行う場合は5万~10万円 |
| お盆 | 3万円~5万円 |
| お彼岸 | 3千円~2万円 |
| 一周忌 | 3万円~5万円 |
| 三回忌 | 1万円~5万円 |
| 七回忌 | 1万円~5万円 |
永代供養のお布施の書き方
僧侶に渡すお布施の包み方には、細かなマナーがあります。故人の供養を長くお願いする相手に失礼がないよう、準備には細心の注意が必要です。まずは、お布施に入れるお金のマナーを確認しましょう。
【お布施に入れるお金のマナー】
- お札を入れる向き
お布施では、お札の表面を包みの表側に合わせて入れます。包みから取り出したときに肖像画が目に入るよう、お札の右側を包みの開け口側にそろえることがマナーです。 - 新札を包む
お布施は寺院への捧げものであり香典ではないため、新札、もしくは新札に近いものを使用します。
また、お布施を包む封筒や奉書紙の記載事項にも細かなルールがあります。宗派や地域によっても詳細が異なるケースはありますが、基本を押さえておくことが大切です。
ここでは、お布施の書き方を解説します。
表書きの書き方
お布施を包む白封筒や奉書紙への表書きは、縦書きが基本です。包みの表面中央上部に「お布施」や「御布施」と記入します。お布施と永代供養料を合わせて渡す際は「お布施」でよく、永代供養料のみを渡すときは「供養料」と書きます。市販されている印字済みのお布施袋を使用する際は記入する必要がありません。
「お布施」の下に喪主の姓名を書きます。裏面に姓名や連絡先を明記するときは、名字のみや「○○家」のように葬家(喪家)の家名のみでも問題ありません。しかし、普段からお付き合いのない寺院に依頼する際は、フルネームを記載したほうが親切です。
香典の場合は薄墨を使用して、お悔やみの気持ちを表します。しかし、寺院への捧げものであり、僧侶への感謝を表すお布施の表書きは濃墨を使用します。同じ黒でもボールペンやサインペンはマナーに反するため、避けたほうが無難です。
なお、宗派や地域の慣習によっては形式が異なるケースがあるため、必ず確認しましょう。例えば浄土真宗で永代供養をお願いするとき、お布施の表書きは「永代経懇志」となります。
中袋の書き方
中袋を使用する場合、表面の中央部分にお布施に包む金額を縦書きで記載します。この際に使用するのは、英数字ではなく漢数字の旧字体です。例えば、10万円を包むときは「金拾萬圓也」といった具合です。
裏面の左下には、「郵便番号」「住所」「氏名」「電話番号」を記載します。郵便番号や電話番号、番地には通常の漢数字を使いましょう。
裏面の書き方
中袋を使用しない場合は、封筒の裏面右上に「金額」、左下に「郵便番号」「住所」「氏名」「電話番号」を縦書きで記入します。例えば10万円を包むとき、中袋と同じく金額は漢数字の旧字体で「金拾萬圓也」のように記入し、住所などには通常の漢数字を用いましょう。
裏面(中袋)の情報は寺院が檀家やお布施の管理に使用するため、省略せず正確に記入するのがポイントです。寺院や地域によっては記載内容が指定されている場合もあります。可能であれば、事前に確認するとよいでしょう。
金額の書き方
中袋の表面や中袋の裏面に金額を書く際に使用するのは、英数字ではなく漢数字の旧字体です。また、金額の前には「\」ではなく「金」、数字の終わりには「円」ではなく「圓」を使い、地域によっては最後に「也」を添える場合があります。
金額に使用する旧字体の漢数字は、下記の通りです。
| 【旧字体対応表】 | |||
|---|---|---|---|
| ¥ | 金 | 7 | 漆 |
| 1 | 壱 | 8 | 捌 |
| 2 | 弐 | 9 | 仇 |
| 3 | 参 | 10 | 拾 |
| 4 | 肆 | 千 | 阡または仟 |
| 5 | 伍 | 万 | 萬 |
| 6 | 陸 | 円 | 圓 |
「一」や「二」のように、現在使用されている漢数字は読み間違いを起こす可能性があるため、旧字体を使用しています。
実際に金額を書く場合の記入例は下記の通りです。
| 【記入例】 | |
|---|---|
| ¥3,000 | 金参仟圓也 |
| ¥150,000 | 金拾伍萬圓也 |
永代供養のお布施の包み方
お布施の渡し方や包み方にもマナーがあります。お布施を渡す際、カバンや財布からむき出しのお金を取り出してそのまま手渡しするのはマナー違反です。お布施は、奉書紙か封筒で包みます。さらに持ち歩く間は袱紗(ふくさ)に包んでおき、渡す際は袱紗や切手盆の上へ乗せて差し出しましょう。表書きは相手から読める向きに直します。
お布施を渡すタイミングは決まっていません。しかし、寺院によっては決まりがあったり銀行振込だったりするため、事前に確認したほうがよいでしょう。特に指定がないときは、葬儀であれば開始前もしくは終了後、法要・法事では読経終了後が最適とされます。永代供養料にお布施が含まれている場合、納骨時のお布施は必要ありません。
ここでは、お布施を包む手順を奉書紙・封筒に分けて紹介します。
奉書紙での包み方
お布施は半紙と奉書紙で包むのが正式な方法であり、具体的には半紙で中袋を作り、その中袋を奉書紙で包みます。詳しい手順は下記の通りです。
| 【半紙で中袋を作る】 | |
|---|---|
| 1 | 半紙の裏面を上にして縦に置く |
| 2 | 右上の角を左側の端に沿わせ、左上の角が45度になるように折る |
| 3 | お札の肖像画を上にして入れ、谷折りの線とお札の端を合わせる |
| 4 | お札の両端に合わせて、半紙の右下と左上を内側に折る |
| 5 | お札の上下に合わせて右から回転させるように折る |
| 【中袋を奉書紙で包む】 | |
|---|---|
| 1 | 奉書紙の裏面を上にして縦に置く |
| 2 | 中袋を中央よりやや左下に置く |
| 3 | 中袋に合わせて奉書紙を左・右・下・上の順番に折る |
半紙・奉書紙ともにざらざらした面が裏、つるつるした面が表です。
白封筒での包み方
奉書紙が入手できなかった場合は、白封筒でも代用可能です。白封筒で包むときは表書きとお札の表面を合わせ、右側を上にして封入します。ただし、白無地が基本であり、郵便番号の欄がある封筒や柄が印刷された封筒の使用は控えましょう。お布施用に表書きが印字されているタイプの封筒は問題ありません。
また、「不幸が重なる」ことを連想させるため、二重封筒は避けたほうが無難です。水引は基本的に不要ではあるものの、地域によって慣習が異なるため事前に確認しましょう。
まとめ
永代供養では永代供養料に納骨法要時のお布施が含まれているため、個別でのお布施が基本的に不要です。ただし、葬儀や一周忌、三回忌といった法要に伴うお布施は含まれていません。基本的にはお布施を含んだ金額が提示されますが、読経料、お車代、戒名料などが別途でかかる場合もあり、読経料では15万円以上が相場です。
お布施を包む白封筒や奉書紙の表書きは縦書きが基本であり、包みの表面中央上部に「お布施」「御布施」などと記入します。中袋の表面、中袋の裏面に金額を書くときは英数字ではなく、漢数字の旧字体を使用しましょう。お布施を渡す際は奉書紙か封筒で包むのがマナーです。