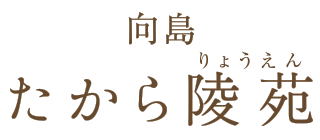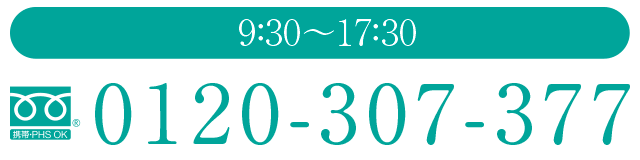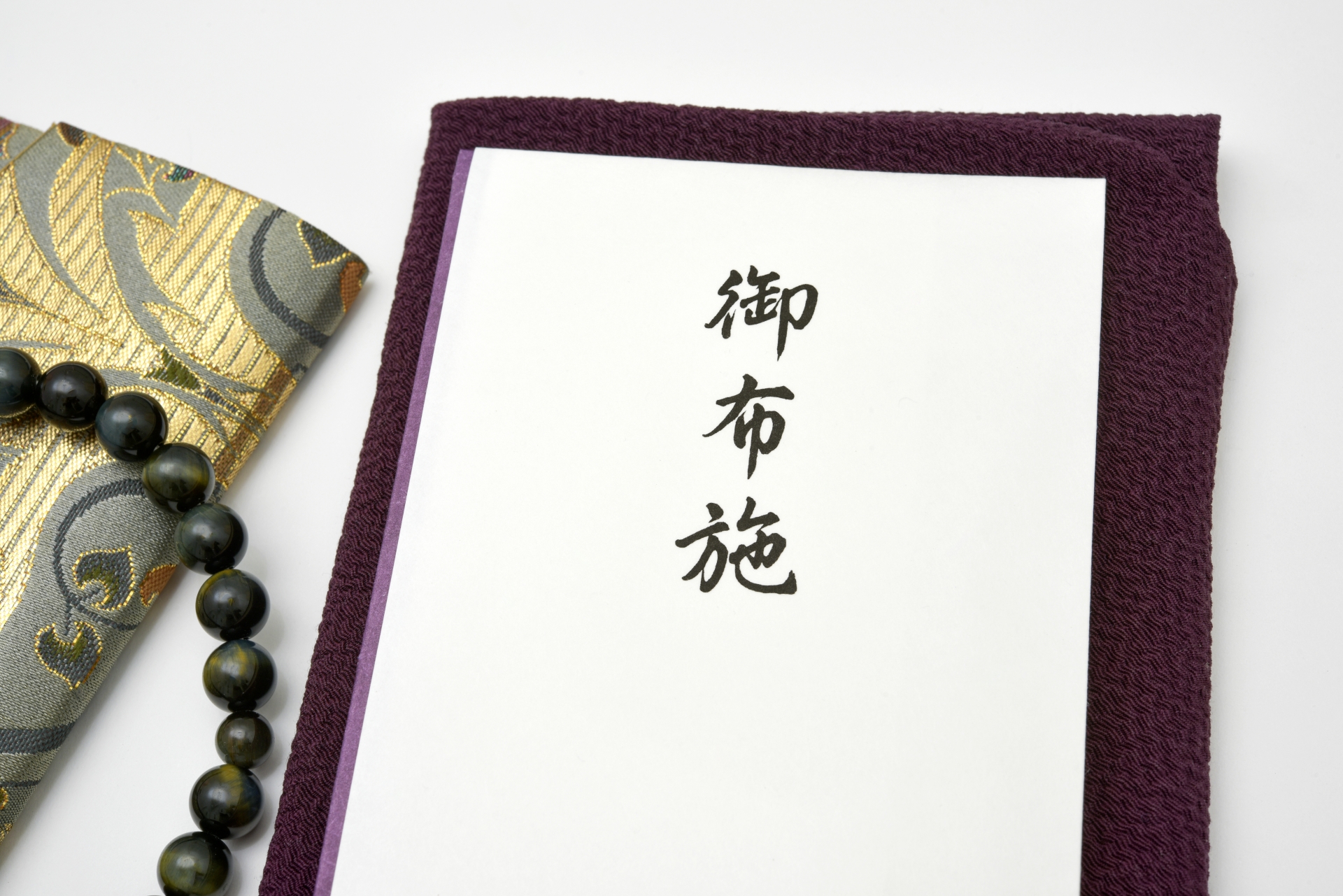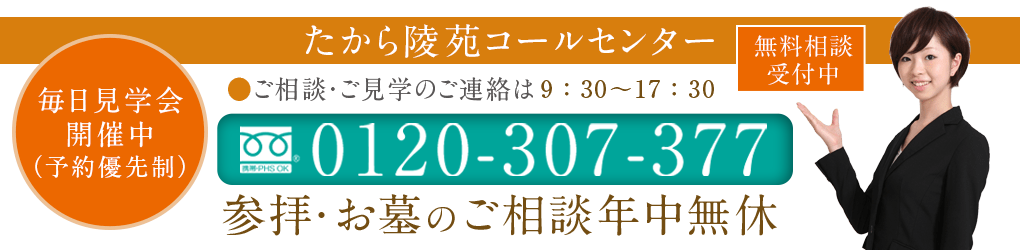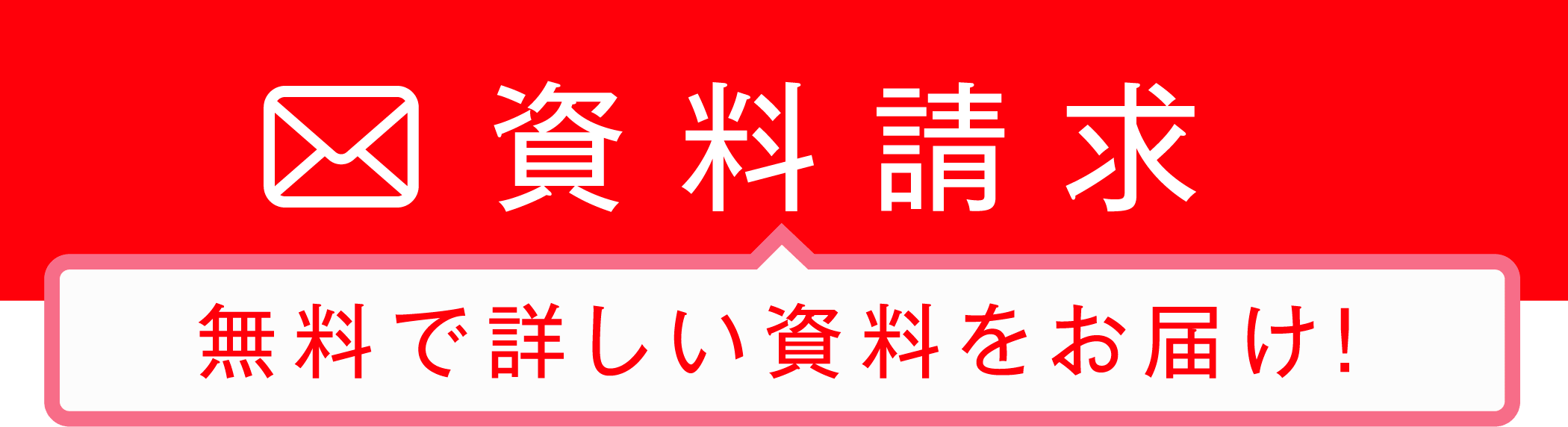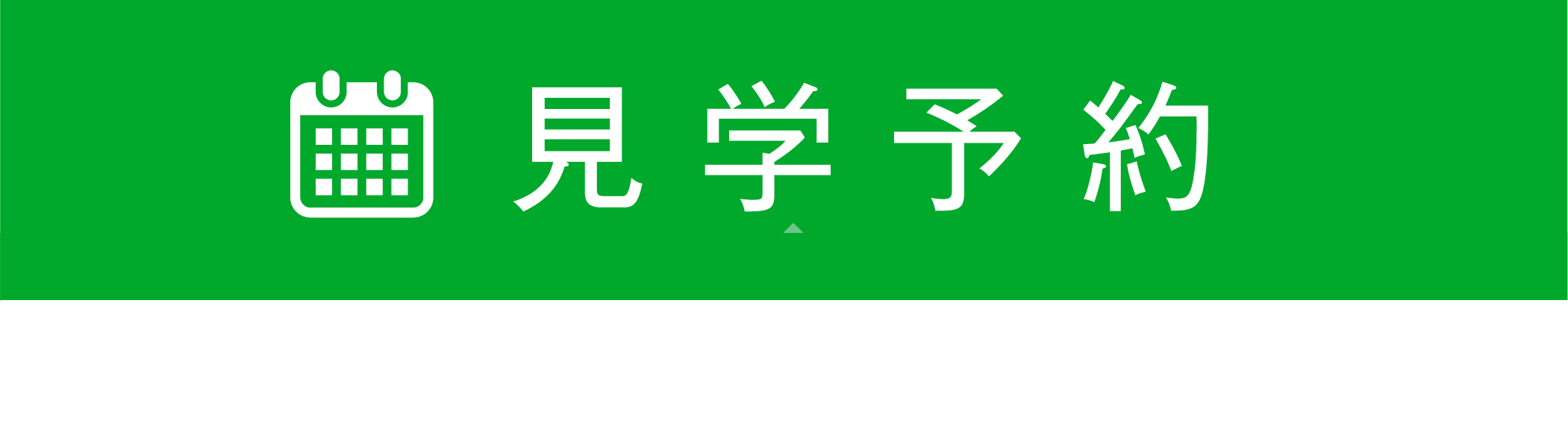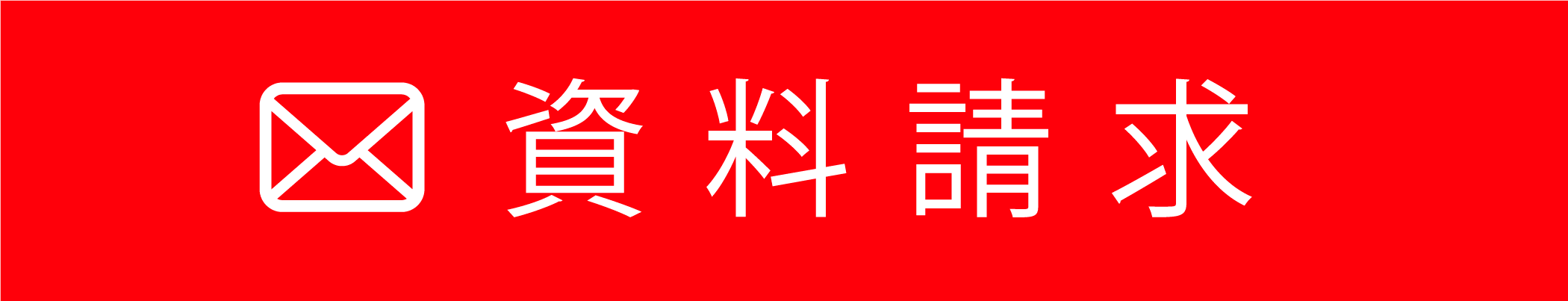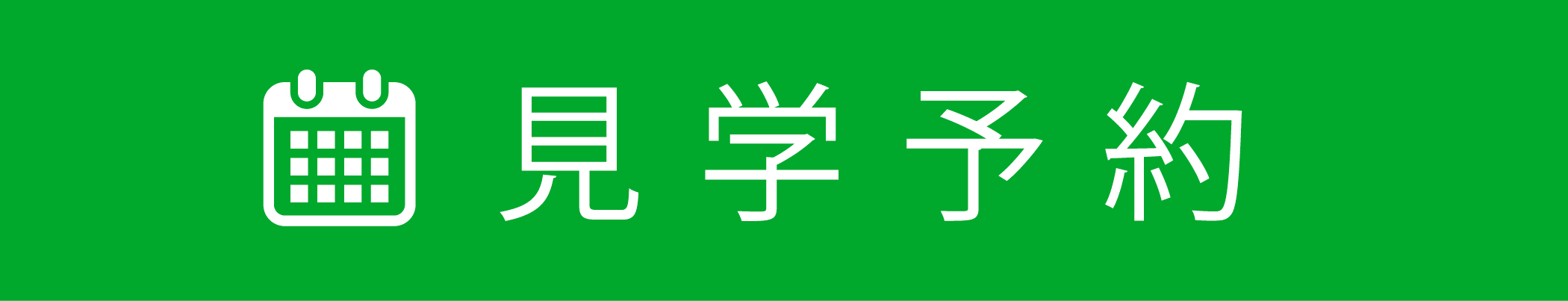正しいペット供養の方法 | 向島たから陵苑


ペット供養のやり方で悩んでいる方は少なくありません。どのような方法が適しているのか、自宅供養すべきか納骨堂を利用すべきか意外と難しいものです。ここでは一般的なペット供養の方法をはじめ、納骨堂の良さを紹介しています。現在ペットを飼っている方も、万が一のときに備えて確認しておきましょう。
亡くなった後はまずどういう対応をする?
ペットも大切な家族です。亡くなったときはきちんと供養し、天国へ届けてあげましょう。ここでは亡くなった後、まずどういう対応をすべきか解説しています。
体をきれいにしてあげる
最初に行うのは遺体の安置です。正しい姿勢でゆっくり寝かせあげます。体をきれいにするため、汚れても良いように大きめのビニール袋などを敷いてあげると清潔に保つことができます。そのうえに新聞紙を敷き、ペットをゆっくり移動してあげましょう。ペットの場合、死後2~3時間で硬直すると言われていますから、そうなる前に素早く対処する必要があります。ですから、安置の時点できちんと整えてあげることが大切です。もし口が開いていたら手を使って閉じてあげてください。
正しく安置してあげたら、今度は体をきれいにしてあげましょう。ブラッシングで毛並みを整え、尻尾も揃えてあげます。なるべく棺の外で行うことで全身をきれいに整えることができます。また口や肛門から体液が出ないようにコットンで詰め物をするのも忘れないようにしてください。
棺に遺体を移してあげる
体をきれいにしてあげたら、棺または箱に移動させます。箱を使用する場合は遺体がきちんと収まるように丈夫なものを用意してあげてください。中には毛布を敷き詰め、棺・箱の下にはビニール袋またシートを敷きます。保冷剤は溶けてしまうので、敷くときはタオルや手ぬぐいなどで包んであげると安心です。保冷剤がない場合は氷袋でも対応できます。そのうえに毛布で包んだペットを納め、布団をかけてあげたら遺体の移動は完了です。
腐敗の進行を防いであげる
先ほど保冷剤や氷袋を敷くと説明しましたが、その理由は腐敗や損傷などを防ぐためです。冷却することでそれらの進行を遅らせることができるので、必ず用意してください。ただ保冷剤や氷袋は溶けてしまうため、ドライアイスのほうが長時間低温を保つことができます。とにかく遺体を冷やしてあげることが大切でしょう。
お供え物をしてあげる
最後にお供えです。好きだったものを用意し飾ってあげます。生花は全体に敷き、可能であれば供養台を設けてあげましょう。ここにろうそくや線香を祀ります。
同居ペットへの配慮
飼育中のペットと2人で暮らしている方は、万が一自分がペットよりも先に亡くなった場合、遺されたペットがひとりにならないように準備をしなければなりません。
家族や知人に相談する
ペットが取り残されたとき、代わりに引き取ってもらえるか家族や知人に相談しておくことで、もしもの時の引き取り手が見つかる可能性があります。
ただしその場合、引き取ってからのペットの食費やお世話にかかる費用を相手持ちにさせるのは負担になってしまうので、こちらで費用を支払っておくなどの取り決めが必要になります。
費用をきちんと受け取ってペットのために使ってくれる、信頼のできる相手を選ぶ必要があるでしょう。
ペット相談サービスに相談する
無料でペットとの生活について相談できるサービスに連絡し、死後のことについてアドバイスを受けておく方法もあります。
「ペットについて誰にも相談できない」「まわりから反対されて飼育しているので先々が不安」といった話しにくいことも気軽に相談できます。
ペット可能な物件に入っておく
戸建てやマンションなど、独立した物件にペットと入居している場合、自分の身に何かがあったときにペットが孤立してしまいます。
ペットを建物全体で飼育できる物件・ペット同伴可能なシェアハウスや介護施設に入居することで、自分自身の死後もペットのお世話を請け負ってもらうことが可能です。
火葬後の5つの供養の方法
もちろん、火葬後の対応も重要です。ペットの供養方法は5つあります。
1.合同墓
一般的に火葬後は「合同墓」または「個別墓」から選ぶことができます。合同墓とは他のペットと一緒に埋葬する方法で、個別墓は言葉のとおり単独で埋葬することを意味します。ほとんどは合同墓を選択するケースが多いですが、金銭的に余裕がある方は個別墓を選んでも良いでしょう。
合同墓の場合、火葬後は霊園側に預けることになります。他のペットと埋葬するためあとで個別墓にすることは難しいですが、年間管理費や追加費用などがかからないので、なるべく費用を抑えたい方には適しています。またペットが寂しい思いをしないという点もメリットになります。霊園によっては定期的に法要を行っているところもありますから安心でしょう。
2.自宅(忌日まで)
自宅で供養する方法は“忌日まで”と“永遠に”で異なります。忌日まで自宅で供養する場合、期限が決まっているのですぐに埋葬したくないという方には大変適しています。気持ちの整理がつくまで遺骨と一緒にいられるのも良いでしょう。忌日後はきちんと埋葬できるように、埋葬方法は事前に決めおくことをおすすめします。
3.自宅(永遠に)
永遠に自宅で供養することも可能です。ただ大型ペットの場合、場所を取ってしまうため注意しなければいけません。どうしても自宅供養したい方は、自宅の庭にお墓を建ててあげることもできます。金銭的に余裕がなければ難しいですが、いつでもペットをそばに感じたい方には良いでしょう。室内で供養する場合でもペットが安心して成仏できるように祭壇を用意しておいてあげてください。
4.手元供養
霊園で埋葬するけれど、残りは手元に残しておきたい場合の供養方法です。遺骨の一部を砕いたものを容器に入れて保管することになります。自宅で保管するという意味で、デザイン性の高い容器も売っています。インテリアにこだわっている方はそちらを利用してみるのも良いでしょう。ペンダントに遺骨や写真を入れる方法もあります。
5.散骨
散骨は粉々になるので十分理解して選択しなければいけません。また個人では対応できないため必ず専門家に依頼することになります。埋葬許可証の提出も必要になるため事前準備が欠かせません。
納骨堂でペット供養をするメリット・デメリット
ペットの供養方法で悩んだら、納骨堂に相談することも可能です。ここでは納骨堂に依頼した場合のメリット・デメリットを解説します。
◎メリット
きちんと供養してくれるので安心です。また気持ちの整理をしたい場合、納骨堂なら自宅から離れているので引きずる心配がありません。他にも個別区画で供養できたり、お供えや管理をしてもらえるのも助かります。納骨堂によっては定期的に法要をあげてくれるところもあります。ペットと人が一緒に入れる納骨堂もあるので、納骨堂を選ぶ際に候補に加えるのもいいでしょう。
◎デメリット
一方でデメリットもあります。それは、年間管理費用が1~3万円程度かかることです。無料で供養してくれる霊園に比べると少し高く感じるかもしれません。さらに、もしペットと一緒にお墓に入りたいと思っている人であれば、契約前にしっかり確認しておく必要があります。
当サイトでは、ペットの永代供養について別の記事にてご紹介しております。
詳しくは、ペットの永代供養とは?詳しく解説!の記事をご覧ください。
供養のやり方に悩んだら納骨堂に依頼しよう
自分でも供養することはできますが、保管するスペースが必要だったり、お墓を建てる場合は費用もかかります。しかし納骨堂なら年間管理費用はかかるもののきちんと管理してくれるので安心です。
いつまでもペットを大切にしたい、ペットと一緒にお墓に入りたいという方は、「向島たから陵苑」にお任せください。納骨を行わなければ、ペットの納骨が行われている期間も護持会費は無料となります。死後も愛しいペットと離れたくないという方はぜひ検討してみてください。
向島たから陵苑では、ペット供養も可能な納骨堂もご用意しております。
墨田区で納骨堂をお探しの方はコチラからご覧ください。