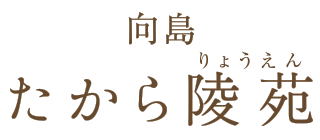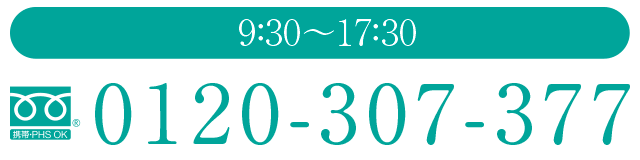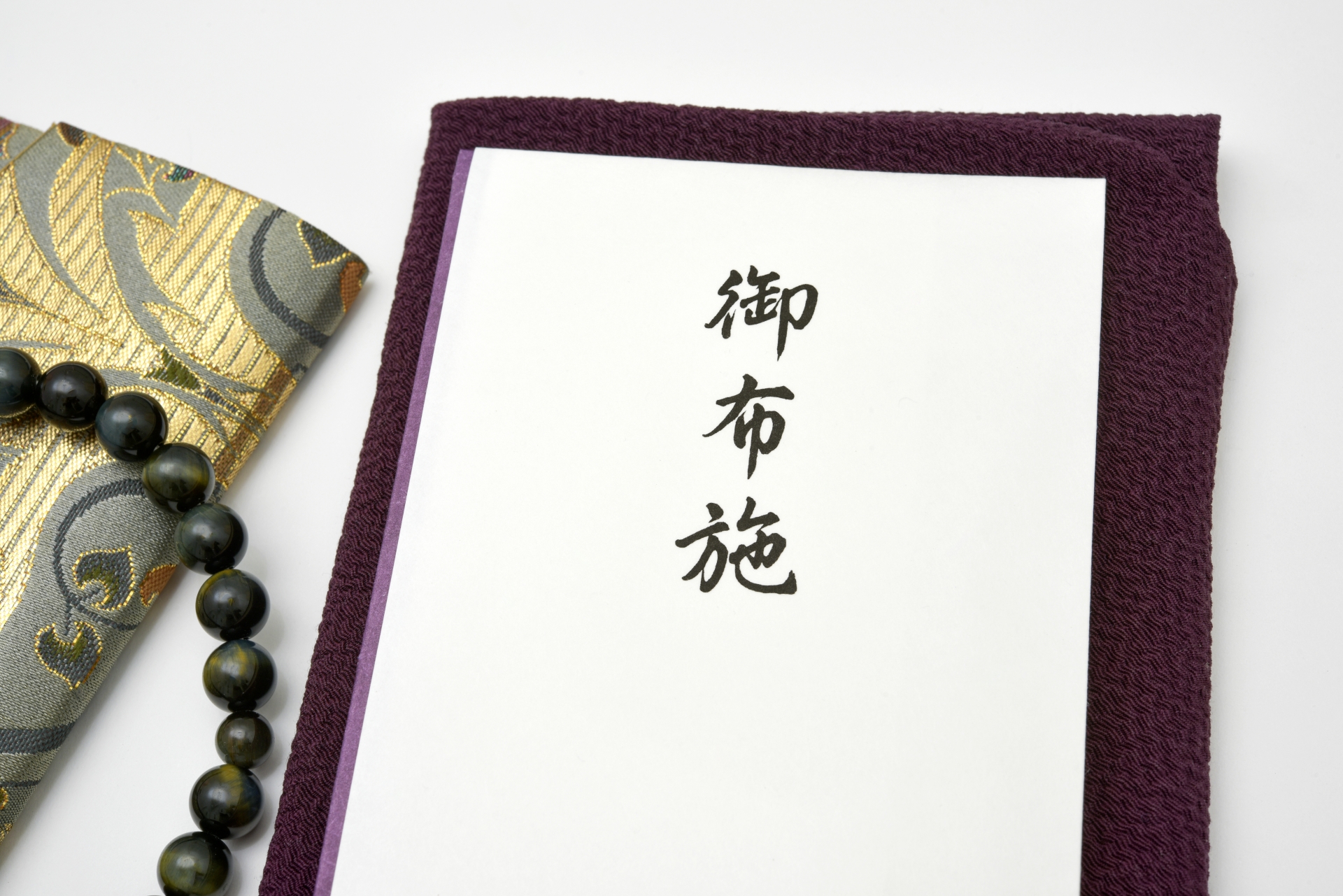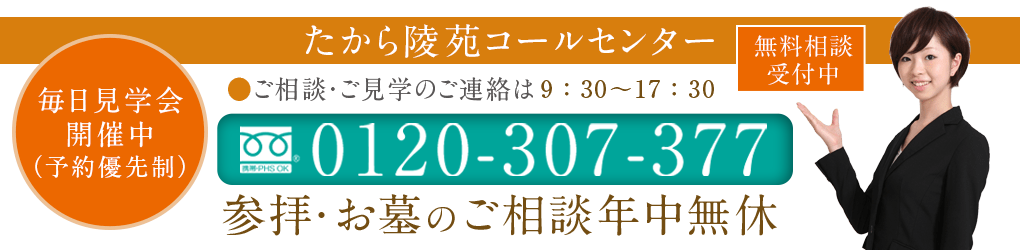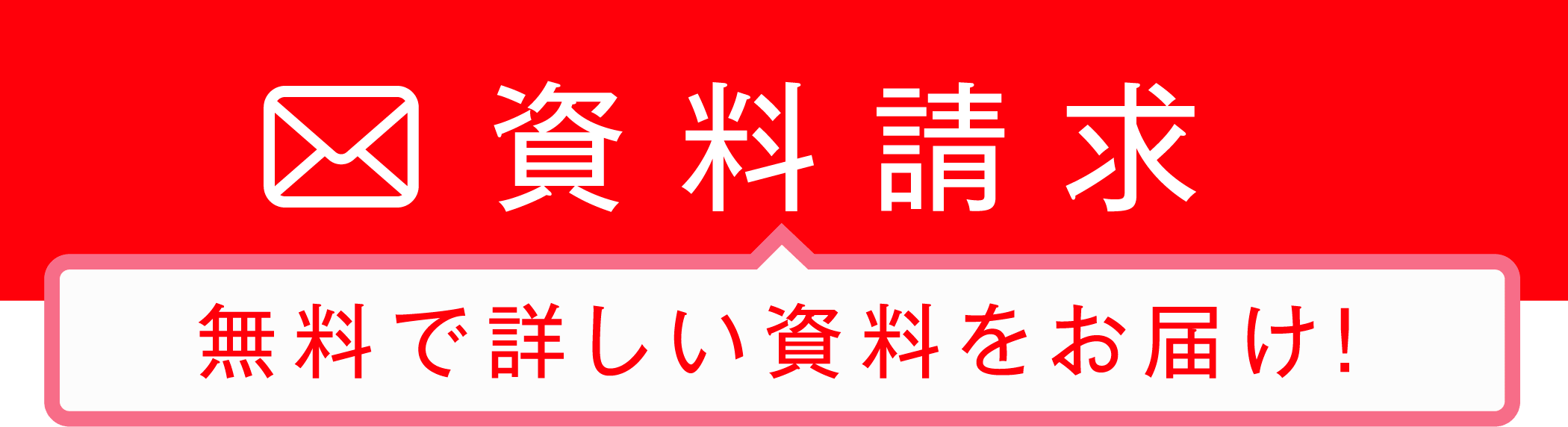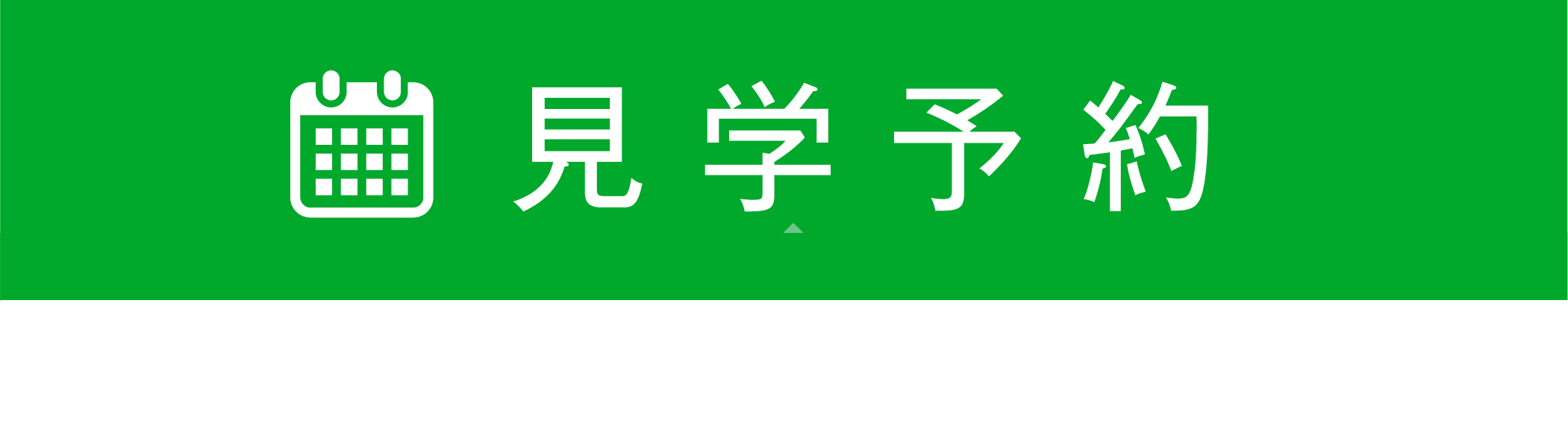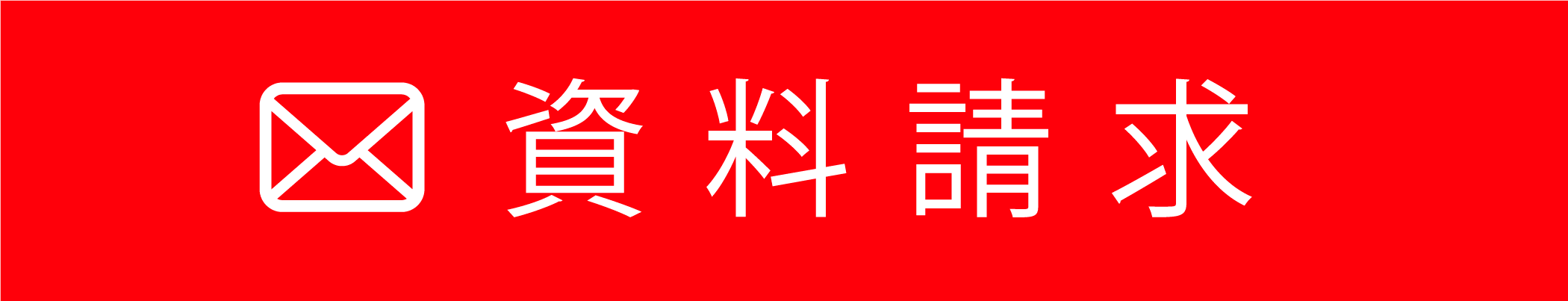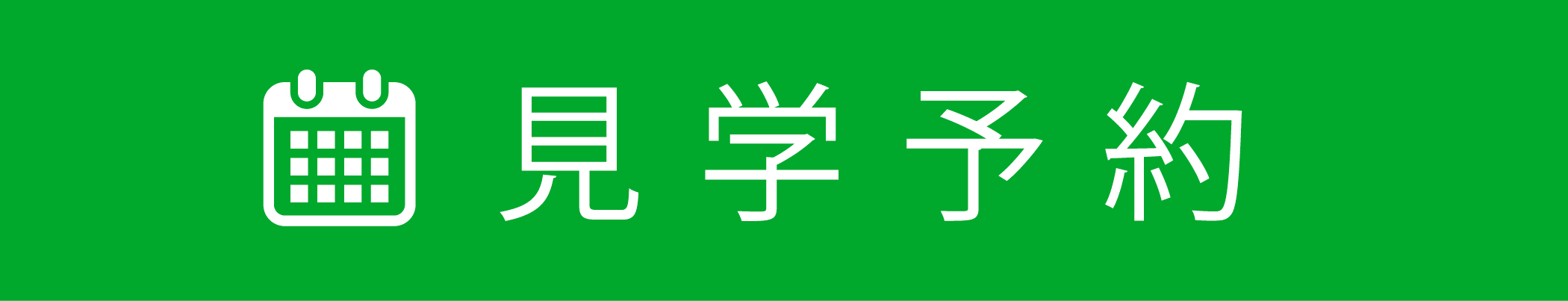納骨堂でのマナーを確認!お供え物やお布施、お参りの方法 | 向島たから陵苑


納骨堂は故人が眠っている場所なので、きちんとマナーを守ってお参りをしなければなりません。
何を持っていけば良いのかわからない、読経や儀式を執り行ってもらう参院のお布施の金額に悩んでいる、お参りの方法を知りたいといった方のために基本的なマナーをご紹介します。
納骨堂での持ち物に関するマナー
納骨堂は他の利用者の方もいるので、マナーはしっかり守りましょう。
服装については喪服である必要はなく、基本的に自由ではあるものの、持ち物のマナーを確認しておくことが大切です。 おさえておきたいポイントをご説明します。
基本的に手ぶらでも良い
納骨堂は必ずこれを持っていかなければならないといったものはなく、手ぶらでも構いませんが、数珠やお供え物を持っていくのが一般的です。
何かお供え物を持っていく場合はそのまま置いてくるのではなく、持ち帰りましょう。 また、お供物は可能であるものの、アルコール類を持ち込み禁止にしているところもあります。
掃除道具は必要ない
屋外に建てられている一般的な墓石のあるお墓は、お墓参りをする際に掃除をする必要がありますが、納骨堂の場合には、掃除をする必要はありません。そもそも納骨堂は屋内にあるので汚れませんし、骨壷の収蔵スペースのほこりを軽く払う程度の掃除で十分です。 バケツや桶、ひしゃく、タオルなどは不要です。
生花のお供えができるかは事前に確認
墓地などにお墓参りに行く際には生花を持って行きますが、納骨堂の場合は生花のお供えができない可能性もあるのであらかじめ確認しておきましょう。個人のスペースが狭く、供えるスペースがないためです。
個人のスペースに飾ることはできないものの、別のところにお供えできる納骨堂もあるので、そのあたりも事前に確認しておくことをお勧めします。
火気厳禁の施設もある
お参りをする際に線香やローソクを持っていく方もいますが、納骨堂の中には火気厳禁のところもあります。
これは、火事のリスクを考えているからです。 納骨堂には非常に多くの方のご遺骨が収蔵してあるわけなので、万が一火事を起こしてしまったら大変です。必ずルールを守りましょう。
納骨堂でのお布施のマナー
納骨堂で読経や儀式を執り行ってもらった際には、僧侶に対して供養をしてもらう謝礼の気持ちとしてお布施が必要です。費用の目安や私型のマナーをご紹介します。 なお、ただ納骨堂にお参りする際のお布施は不要です。
お布施について
お布施は謝礼として渡すものなのですが、具体的な料金設定がありません。
お経を上げてもらうことに対するお礼としてお渡しするものですが、自分が包める金額で相談してみましょう。 また、お布施のほかに納骨堂まで出向いていただいた交通費としてお車代が5千円~1万円ほど必要です。それから、式の後に行われる会食を辞退された場合には御膳代として同じく5千円~1万円ほど必要なので、新札で用意しておきましょう。 用意したお金は市販の白い封筒に入れるか、奉書紙と呼ばれる紙で包みます。
いつ渡すのか
渡すタイミングについて特に決まりはありませんが、納骨堂に到着した僧侶に挨拶をする際か、式の終了後にお礼の挨拶をする際に渡す方が多いです。お礼の挨拶とともに渡しましょう。
納骨堂でのお参りのマナー
どのようにお参りをするのかについての作法を多く紹介します。
基本的なマナー
他にお参りに来ている方もいるので、大きな声で話しをしてはいけません。
また、寺院内にある納骨堂ではお寺の方にもしっかりと挨拶をし、気持ちよくお参りをしてみてはいかがでしょうか。
全体の流れ
お供え物として持っていけるものは納骨堂によって変わるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
また、ご本尊が納骨堂の内部に祀られている場合、まずはご本尊にお参りをしてから納骨堂に行くのが一般的な礼儀作法だといえます。納骨堂の参拝スペースでは、生花やお線香をお供えするスペースが別途設けられていることも多いため、納骨堂のルールに従わなければなりません。 納骨堂のお墓参りのやり方などについては通常と同じです。わからないことなどがあれば、施設の方に直接確認してみましょう。
また、近年はマンション型とも呼ばれている自動搬送型が増えており、こちらの場合は専用のICカードをかざすことによって参拝スペースまでご遺骨が運ばれてきます。最新のシステムであり、焼香ができるような仕組みを整えているところもあるので、各納骨堂のシステムやサービスを事前に確認しておくのも良いでしょう。
事前にマナーを確認しておくと安心
納骨堂での守るべき礼儀作法についてご紹介しました。それほど堅苦しく考える必要はありませんが、最低限の礼儀作法についてはしっかり準備をしておきましょう。
納骨堂の場合は他にも利用者の方がたくさんいるので、他の方に迷惑をかけないように十分注意が必要です。 また、お供え物や線香などに関しても一般的なお墓とは取り扱いが異なるので注意点を確認してからお参りをしましょう。
当サイトでは、納骨堂の利用で考えられるトラブルを別の記事にてご紹介しております。
詳しくは、納骨堂の利用で考えられるトラブルとメリットの記事をご覧ください。
髪型や身なりに関するマナー
納骨堂への参拝に着ていく服については、故人が亡くなってからどれだけの期間が経ったかで変化します。
日本では、四十九日と呼ばれる日までは喪服での参拝が基本となり、通夜や葬式の際に着用した喪服と同様の身なりで参拝します。
四十九日までの服装マナー
四十九日までの際に着用する喪服は、それぞれ以下の通りとなります。
- ・男性:黒スーツ+黒ネクタイ+黒い革靴
- ・女性:黒ジャケット+黒スカート+黒いパンプス(ブラックフォーマル)+パールのネックレスなど
故人が亡くなり、葬儀・火葬までを済ませたあと、納骨式まで日が空くようであれば一度クリーニングに出しておくと安心です。
はじめて納骨式に参加する方は、四十九日の期間中に上記の喪服一式を用意しておきましょう。
四十九日後の服装マナー
四十九日を過ぎたら、墓地や墓所と同じく普段着(平服)で参拝ができますが、数珠や念珠は四十九日までと同じで、それぞれの宗派に即したものを持参してください。
髪型や身なりに関する服装規定も、僧侶を呼んでの読経や宗教上の行事以外では気にすることなく、普段の服装で参拝を行うことができます。
ただし、一般常識として派手な服や露出の多い服装、TPOにそぐわない格好は避けましょう。
納骨堂も墓地と同じ「墓所」ですから、奇抜さを感じさせる格好にする必要はなく、落ち着いたトーンの身なりと髪型を心がけてください。
向島たから陵苑では、ペット供養も可能な納骨堂もご用意しております。
墨田区で納骨堂をお探しの方はコチラからご覧ください。