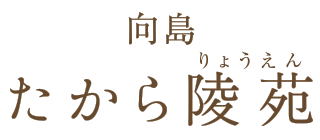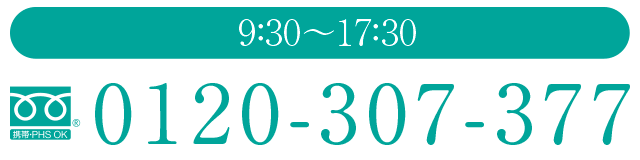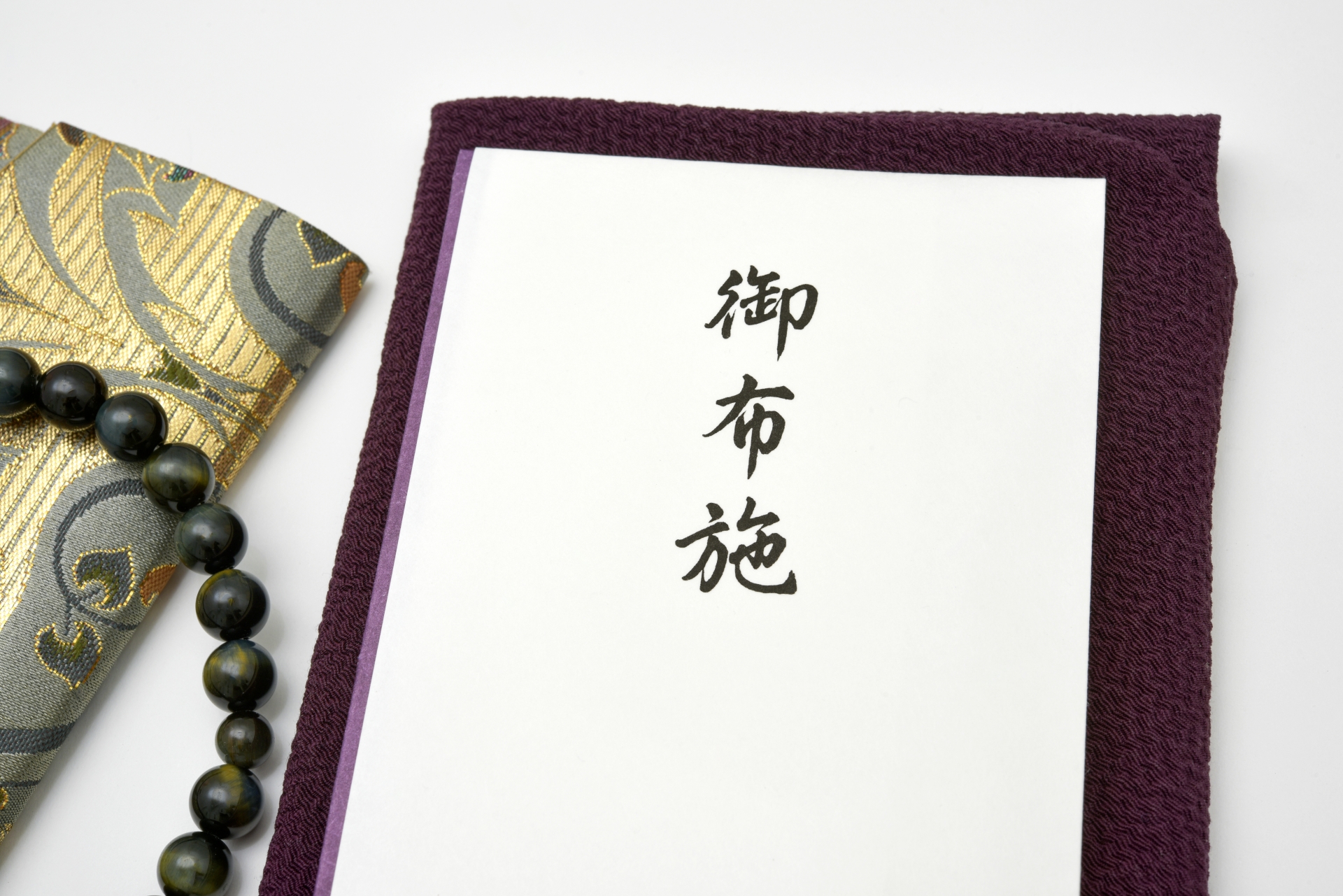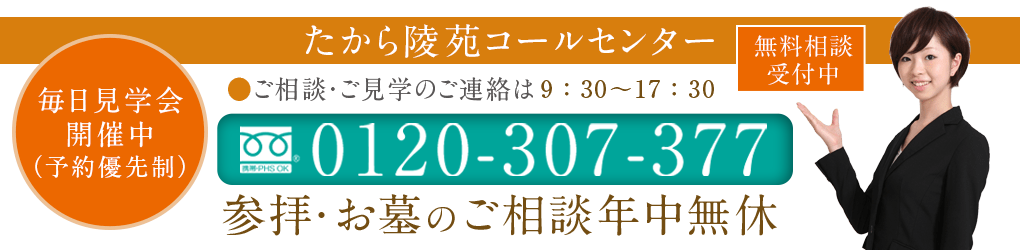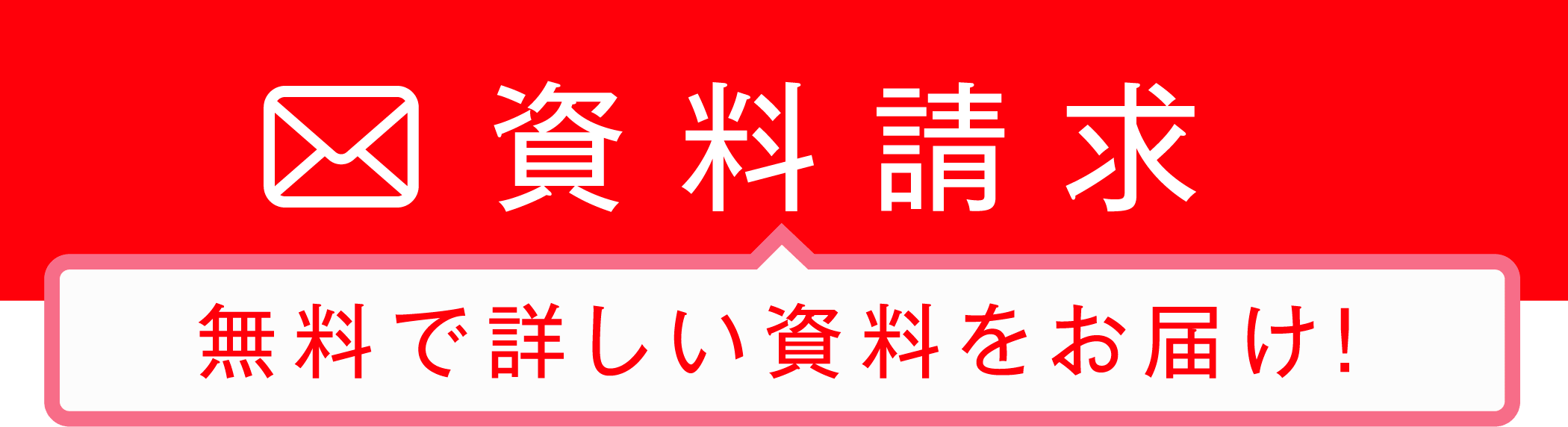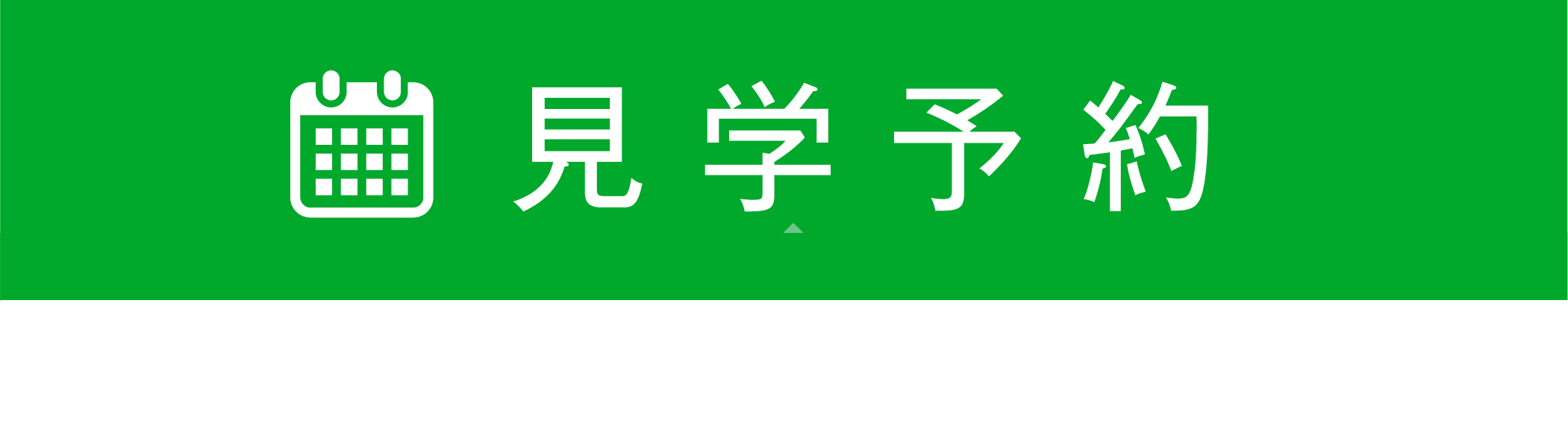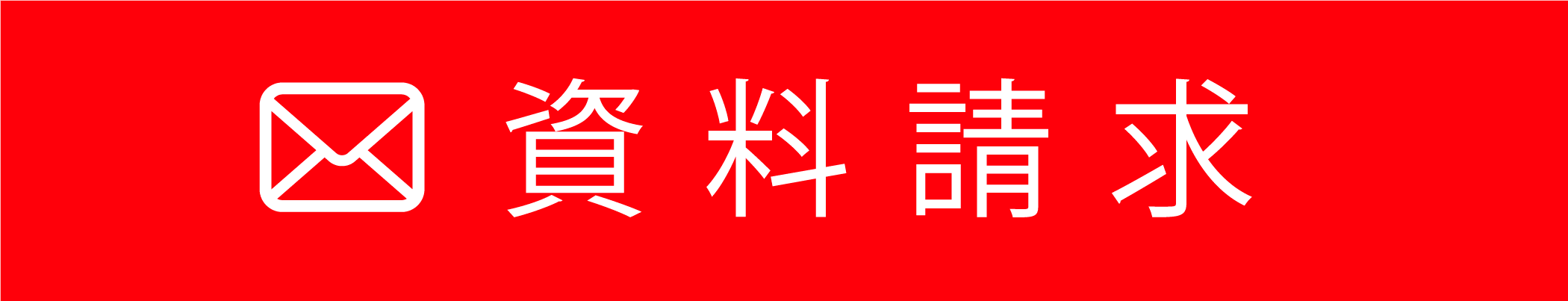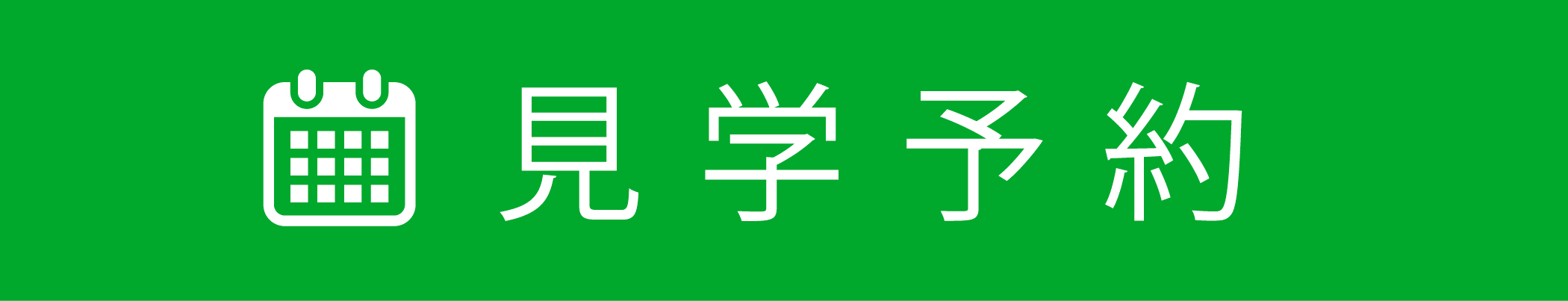納骨堂の費用相場を種類別に解説!内訳や費用を抑える方法も | 向島たから陵苑


都市内にあり気軽にお墓参りができたり、お墓を管理する負担が少なかったりする点から近年では納骨堂が注目を集めています。しかし、納骨堂には複数の種類と運営主体があり、費用に大きな差があることが特徴です。納骨堂を検討中の方には、できるだけ費用を抑えて購入したいという方もいるのではないでしょうか。
当記事では、納骨堂の費用相場を納骨堂の種類と運営主体に分けて紹介します。費用の内訳や費用を抑える方法を知りたい方も、ぜひご一読ください。
納骨堂とは?一般的な費用相場を解説
納骨堂とは、遺骨の入った骨壺を室内の収骨スペースに安置して、そのまま管理するための施設です。
納骨堂の建物内には多くの収骨スペースがあり、個人や家族などの単位で区画を購入して、遺骨の安置に使用できます。墓石を購入する必要がないため、お墓にかかる費用を安く抑えられる点がメリットです。
納骨堂の利用にかかる費用は、納骨施設の規模や設備・サービスなどによって異なるものの、一般的な費用相場は約20万~80万円程度です。
納骨堂の費用は誰が支払う?
納骨堂の費用は誰が支払うかは契約者の考え方によって変わります。納骨堂の主な支払いパターンは、下記の3通りです。
(1)親が契約者であり、支払いも親がするパターン
親が自分の墓を購入して、支払いも親自身で行います。親が亡くなった後は、契約者名義を子へと変更する手続きが必要です。
(2)子が契約者であり、支払いも子がするパターン
親の墓を子が購入し、支払いも子が行います。契約者名義は子であるため、親が亡くなった後に名義変更は必要ありません。
(3)子が契約者で、支払いは親がするパターン
親の墓を子が購入し、支払いは親が行います。親から子への生前贈与であり、親が亡くなった後に名義変更は必要ありません。
なお、納骨堂は祭祀財産であるため相続税はかからないものの、生前贈与の場合は価格が110万円を超えると贈与税の対象になる可能性があります。
納骨堂の費用には「護持費」という維持管理費用があります。護持費は一般的には年払いであるものの、たから陵苑では一括払い(50年、30年、20年、13年)のプランをご用意しております。
護持費の年払いを選択した場合は、契約者が亡くなったとき、残された家族が護持費を支払うことになる点に注意しましょう。
護持費の一括払いを選択すれば、支払いパターンの(1)・(3)のパターンでは護持費の支払いが親の負担となり、子の負担にはなりません。
納骨堂の費用の内訳
納骨堂の利用にかかる費用は大きく分けて、最初に支払う初期費用と、継続的に発生する費用の2種類があります。納骨堂の費用相場を知る前に、どのような部分で費用がかかるかを知りましょう。
納骨堂の費用内訳として、主な費用項目を紹介します。
納骨堂の使用料
納骨堂の使用料とは、納骨堂の区画を購入するために支払うお金です。納骨堂の契約時に支払う初期費用の1つであり、一般墓の「永代使用料」に相当します。
納骨堂の使用料は、初期費用の中でも大きな割合を占める費用です。納骨施設の立地条件や規模、購入する区画の種類によって価格が変動するため、予算に合うかどうかを検討しましょう。
永代供養料
永代供養料は、遺骨の永代供養をしてもらう場合に支払うお金です。
永代供養とは、お墓の管理者である霊園や寺院に遺骨の供養をすべて任せることを指します。永代供養を選択すると、残された家族がお墓の祭祀継承者にならず、法要などの手間をかけることを防げます。
なお、永代供養で所定の安置期間が経過した後は、遺骨は個別の安置場所から共同の安置場所へと移されて合葬されます。合葬後も遺骨の供養は納骨堂が行ってくれるため、無縁仏にはなりません。
永代供養の申し込みは一般的に納骨堂の契約時に行う手続きであり、永代供養料は初期費用に含まれます。もちろん、永代供養の申し込みをしない場合は永代供養料は発生しません。
年間護持費
年間護持費は、納骨堂を維持・管理するために支払うお金のことです。「年間」と名称についているように、基本的に年1回の頻度で支払いが発生します。
永代供養を選択した場合には年間護持費がかからないものの、購入した区画で遺骨を安置している期間中は年間護持費を支払わなければならない施設がほとんどです。
年間護持費の一括払いができるプランが用意されている納骨堂もあります。年間護持費の一括払いをする場合は、納骨堂の初期費用に追加して年間護持費を支払うため、継続的に発生する費用を抑えることが可能です。
その他費用
納骨堂費用としては、その他に下記のような料金が発生します。
| 戒名料 | 戒名をつけてもらうときにかかる費用です。 |
|---|---|
| 銘板彫刻料 | 銘板に故人の名前や戒名、没年月日などを彫刻してもらうときにかかる費用です。 |
| 納骨法要代 | 遺骨を納骨堂に安置するときに、お坊さんに読経をあげてもらうときに費用が発生します。 |
| 回忌法要代 | 1周忌や3回忌・7回忌など、節目の法要をするときにかかる費用です。 |
| 仏具代 | 「仏壇型」で、香炉・燭台・花立といった仏具の購入にかかる費用です。 |
| 開眼法要料 | 「仏壇型」で、仏壇に魂を入れる開眼法要をお坊さんにしてもらうために費用がかかります。 |
| カードキー代 | 「自動搬送型」で、遺骨の搬送に必要なカードキーの購入にかかる費用です。 |
| 収蔵厨子代 | 「自動搬送型」で、遺骨を収骨する厨子の費用がかかります。 |
| 位牌代 | 「位牌型」で、位牌の購入にかかる費用です。 |
| 墓石代 | 「墓石型」で、墓石の購入にかかる費用です。 |
納骨堂の種類によっては、その他費用としてさらに別の費用がかかるケースもあります。
【種類別】納骨堂の費用相場
納骨堂にはさまざまな種類があり、種類によって納骨堂の利用にかかる価格は異なります。納骨堂の購入を考えている方は、種類ごとの費用相場を把握しておきましょう。
納骨堂の主な種類を5つ挙げて、それぞれの納骨方法と費用相場を解説します。
ロッカー型
ロッカー型は、コインロッカー型の収蔵庫内に骨壺を安置するタイプの納骨堂です。収蔵庫には骨壺の他に、故人の写真や位牌などを置くことができて、個別に施錠もできます。
ロッカー型の費用相場は約20万~80万円です。
ロッカー型納骨堂では1人用・夫婦用・家族用といった区画が用意されていて、1人用よりも複数人の収骨に対応できる区画のほうが費用が高くなります。「収蔵庫の段は上・中・下のどこか」「高級な素材を使用しているか」も、費用が変動する要因です。一般的には収蔵庫の段が上段にあるほど、また高級な素材を使用しているほど、費用が高くなります。
仏壇型
仏壇型は区画が上段・下段に分かれていて、上段に遺族がお参りをする仏壇、下段に遺骨の納骨スペースを設けているタイプの納骨堂です。
上段の仏壇には、中央に信仰する宗派の本尊が祀られていて、香炉や燭台なども飾られています。下段の納骨スペースは広さがあり、家族用であれば複数の骨壺を設置可能です。
仏壇型の費用相場は約30万~150万円です。
仏壇型納骨堂は一般的に1人用と家族用があり、1人用のほうが費用は安くなっています。
自動搬送型
自動搬送型は、共有の参拝スペースにまで遺骨が自動搬送されるタイプの納骨堂です。普段はバックヤードの収蔵スペースに遺骨を保管していて、参拝に訪れた遺族がパネルにカードキーをかざすと、機械によって遺骨が搬送される仕組みとなっています。
自動搬送型の費用相場は約80万~150万円です。
自動搬送型納骨堂はシステムにお金がかかっていて、他タイプの納骨堂よりも費用相場が高い傾向にあります。市街地から徒歩圏内の立地にある納骨施設が多い点も、費用相場の高さにつながっている要因です。
位牌型
位牌型は、建物内に祀られた位牌に参拝するタイプの納骨堂です。
位牌型の費用相場は約3万~20万円となっています。
位牌型納骨堂には、個別の安置スペースがあるケースと、仏像を中心として複数の位牌が並べられているケースがあります。個別の安置スペースがあるケースは位牌と遺骨が同じ場所に置かれていて、個別での参拝が可能です。
対して複数の位牌が並べられているケースでは、位牌とは別の場所に遺骨が保管されています。参拝では仏像に対して手を合わせる形となり、個別での参拝はできません。
墓石型
墓石型は、建物内に墓石が建立されているタイプの納骨堂です。墓石が室内にある点以外は一般墓と違いがなく、普通のお墓と同じ感覚で参拝ができます。
墓石型の費用相場は約100万円~です。墓石費用がかかる上に、墓石の設置場所にも高額な使用料がかかるため、他タイプの納骨堂よりも費用相場が高くなります。
また、墓石型納骨堂を購入する場合は、万が一の墓じまいにかかる費用がいくらかかるかも調べておくことが大切です。
【運営主体別】納骨堂の費用相場
納骨堂の費用は、施設の運営主体によっても異なります。どのような運営主体が運営する納骨堂であるかによって利用にかかる費用が変わるため、運営主体ごとの特徴と費用を確認しましょう。
3つの運営主体別に、納骨堂の費用相場と特徴を紹介します。
寺院納骨堂
寺院納骨堂は、寺院が運営主体となっている納骨堂です。寺院と言ってもほとんどの施設は宗派を問わずに納骨ができて、寺院による手厚い供養を受けられます。
寺院納骨堂の費用相場は約20万~100万円です。
寺院納骨堂の中には利用にあたって檀家に入る必要があったり、戒名や法要を寺院に任せなければならなかったりなど、細かなルールが定められているケースもあります。費用以外に、どのようなルールがあるかを見ることが大切です。
寺院納骨堂の管理は運営主体である寺院の住職が行うため、住職の人柄もチェックしましょう。住職が信頼できる人柄であれば、安心して遺骨の管理を任せられます。
公営納骨堂
公営納骨堂は、県や自治体などの公的機関が運営主体となっている納骨堂です。公営納骨堂は運営費の大部分が税金で賄われていて、利用にかかる費用が安いという特徴があります。
公営納骨堂の費用相場は約20万~60万円です。短期納骨や一時収蔵の場合はさらに安くなり、1柱あたり約7千~2万円で利用できるケースもあります。
公営納骨堂は公的機関が運営しているため、運営が安定している点がメリットです。一方で、施設自体の数が少なく、利用希望者の競争率が高いというデメリットがあります。公営納骨堂は収蔵期間が短いケースが多い点にも注意してください。長期収蔵の期限は長くても30年であることが多く、中には収蔵期間が短い一時収蔵納骨堂もあります。
民営納骨堂
民営納骨堂は、民間法人が運営主体となっている納骨堂です。公営納骨堂と比較すると費用相場は高くなる傾向があるものの、設備やサービスが充実していて、手厚い供養が期待できます。
民営納骨堂の費用相場は約50万~100万円です。家族用の納骨堂では費用が100万円を超えるケースもあります。
民営納骨堂は施設の数が多く、利用できる施設を探しやすい点がメリットです。駅から徒歩圏内や、バス停が近くにある場所に立地している施設が多く、納骨堂への参拝をしやすい魅力もあります。
納骨堂と一般墓や樹木葬の費用の比較
納骨堂の利用を検討している方で、よく比較されるのが一般墓や樹木葬です。納骨堂の費用相場を理解した上で、一般墓や樹木葬の費用とも比較をして、どのようなお墓の形が合っているかを決めましょう。
以下では、一般墓・樹木葬のそれぞれの特徴と費用を紹介します。
一般墓
一般墓とは、屋外の墓地で区画を購入して墓石を設置するタイプのお墓です。日本では古くからあるお墓の形であり、お墓と聞いて一般墓をイメージする方も多いでしょう。
一般墓のお墓を購入する場合は、初期費用として「墓地の区画購入費用(永代使用料)」と「墓石の購入費用」がかかります。
購入後にも、墓地の維持管理に必要な「年間管理費」や「墓地・墓石の清掃費」、「墓石の補修・修繕費」などが継続的に発生します。
一般墓の費用相場は約100万~350万円です。墓地の区画と墓石を購入する必要がある分だけ、納骨堂のお墓よりも費用相場は高くなります。
樹木葬
樹木葬とは、屋外の墓地に遺骨を埋葬して、埋葬場所の目印に樹木を植えるタイプのお墓です。
樹木葬のお墓を購入する場合は、初期費用として「永代使用料」と「埋葬料」、石碑や銘板などを設置する場合は「彫刻料」がかかります。購入後は「年間管理費」も継続的に発生します。
樹木葬の費用相場は約15万~80万円です。ただし、埋葬の方法によって費用には幅があり、個別型や夫婦埋葬型では100万円を超える可能性もあります。対して、他人の遺骨と一緒に埋葬する合祀墓であれば約3万~20万円で済むケースもあるでしょう。
樹木葬のお墓は、納骨堂のお墓と大きな金額差がないため、他のポイントも比較して決めることがおすすめです。
納骨堂の費用を抑える方法
納骨堂の利用にかかる費用は、施設の種類や場所、運営主体が提供しているサービスなどを限定すれば安く抑えられます。
以下では、納骨堂の費用を抑える6つの方法を解説します。
位牌型かロッカー型を選ぶ
さまざまな種類がある納骨堂の中でも、費用を抑えやすい納骨堂の種類は「位牌型」と「ロッカー型」です。
位牌型は位牌と安置スペースの購入、ロッカー型は区画の購入をするだけでお墓として使用でき、他の種類よりも費用を抑えられます。費用をより抑えたい場合には、位牌型は個別の安置スペースが必要ない「複数の位牌と一室で並べる納骨堂」を選びましょう。
ロッカー型は、高級な木材を使用しておらず、位置が下段にある収蔵庫を選ぶほうが費用の節約につながります。
収骨可能人数を最低限で選択する
区画の収骨可能な人数が多いほど、納骨堂の費用は高くなります。納骨堂の費用を抑えるためには、区画の収骨可能人数を最低限にしましょう。
ロッカー型で例を挙げると、1人用の区画であれば約20万~40万円が基本的な費用相場です。対して、夫婦用の区画では約40万~80万円が費用相場となります。
安置する遺骨が1人分である場合は、収骨可能人数が1人の区画を選んだほうが費用を安く抑えられます。
郊外の納骨堂を利用する
納骨堂の初期費用としてかかる「納骨堂の使用料」は、基本的に納骨施設がある地域の土地代に左右されています。都市部から離れた郊外であれば土地代が安くなるため、郊外の納骨堂を利用すると費用を安く抑えることが可能です。
ただし、郊外の納骨堂を選ぶと、お墓参りが不便になる可能性もあります。自動車を持っている方は納骨堂近くに幹線道路が通っているか、バスを利用する場合は近くにバス停があるかをチェックすることが大切です。
供養方法と個別安置期間を再確認する
遺骨の供養方法や個別安置期間も、納骨堂の費用に影響するポイントです。
遺骨の供養方法としては、遺骨を個別に供養するプランよりも、他の遺骨と一緒に供養してもらう合祀プランのほうが費用を抑えられます。ただし、合祀を一度選択すると、後になって遺骨を取り出して改葬できなくなる点に注意してください。
遺骨を個別に供養する場合も、基本的には所定期間を個別安置した後に、合祀への切り替えが行われます。個別安置期間が短いほど費用が安く済むため、費用を抑えるには個別安置期間が短い納骨堂を選びましょう。
納骨堂の運営主体を確認する
納骨堂の運営主体は、寺院納骨堂を運営する寺院、公営納骨堂を運営する公的機関、民営納骨堂を運営する民間法人の3つです。3つの中では、公的機関が運営する公営納骨堂が最も費用が安いと言われています。
ただし、公営納骨堂は施設の数が少なく、利用期限などの細かなルールが定められていることもあります。公営納骨堂の利用が難しい場合には、寺院納骨堂と民営納骨堂のどちらのほうが費用を抑えられるかをよく確認しましょう。
複数の納骨堂を比較する
納骨堂はさまざまな施設がプランを提供していて、内容がよく似ているプランであっても施設が違えば費用が大きく異なるケースもあります。希望に合うプランをなるべく安く利用するには、複数の納骨堂を比較することがおすすめです。
気になるプランを用意している納骨堂の候補をいくつかピックアップして、施設見積もり依頼を出しましょう。複数の納骨堂から届いた見積り書を比較すると、希望を満たしつつ費用も安く抑えられるプランを見つけられます。
納骨堂の選び方をもっとよく知りたい方は、下記のページも参考にしてください。
納骨堂を選ぶ際の注意点
納骨堂にはさまざまな施設があるため、選ぶ際は費用面はもちろん、施設への通いやすさや管理・供養の方法など細かなところまで確認することが大切です。
納骨堂を選ぶ際の注意点を3つ挙げて、どのような方法で対策できるかも解説します。
公営納骨堂は抽選になる場合がある
公的機関が運営主体である公営納骨堂は、寺院納骨堂や民営納骨堂よりも費用が安く、人気の高い施設です。
しかし、公営納骨堂は施設数が少ないため、区画利用の募集で希望者が多数集まったときには抽選になる場合があります。公営納骨堂は応募倍率が高く、利用者を抽選で決める方式になると利用できない可能性もある点に注意してください。
公営納骨堂の募集は常にあるわけではなく、納骨堂の新設時や返還墓地ができたときに年1回の頻度で募集される傾向があります。
公営納骨堂を利用したい方は、自治体のホームページをよくチェックして募集情報を見逃さないようにしましょう。抽選に外れた場合を想定して、公営納骨堂以外の施設について情報収集することも大切です。
利用期限が設けられていることがある
納骨堂を利用するときは、区画の利用期限が設けられていることがある点に注意してください。
区画の利用期限とは、区画に遺骨を安置できる期限のことです。個別安置ができる区画で利用期限が設けられていることが多く、「納骨から30年まで」「護持会費を納め続ける限り」など、施設によって期限の条件は異なります。
区画の利用期限を迎えた後は、個別安置が終わった遺骨は合祀されて、他の方の遺骨と混ざった状態になって供養されます。
区画の利用期限を知らずに利用していると、後々トラブルになる可能性があるため、事前に納骨堂の利用期限や合祀になる条件を確認しましょう。遺骨をいつまで個別に供養したいかを考えておくと、適切な利用期限の納骨堂を選べます。
必ず直接見学に行く
近年はホームページ上で内装・設備などの詳細を紹介する納骨堂が増えていて、インターネットで情報収集をするだけでも納骨堂選びがしやすくなっています。
しかし、実際にどの納骨堂にするかを決める際は、必ず納骨堂を直接見学に行くことが大切です。ホームページに掲載されている写真や情報は広告用であり、実際とは違っていたり、情報が古くなっていたりする可能性があります。
また、納骨堂に直接見学に行くと、納骨堂までのアクセスのしやすさやスタッフの人柄も分かります。納骨堂へのお墓参りを考えている方は、お墓参りが大変ではないか、設備の利用についてスタッフのサポートが受けられるかなどをチェックしましょう。
たから陵苑では、納骨堂の見学を受け付けております。安心して利用できる納骨堂をお探しの方は、下記のページから見学予約をお問い合わせください。
納骨堂が向いていない方の特徴
近年では納骨堂の人気が高まっている傾向にあるものの、人によっては納骨堂を選んでから後悔をされるというケースもあります。
納骨堂が向いていない方の特徴を把握し、納骨堂への遺骨の安置が自分に合っているか、後悔をしないかを考えてみましょう。
遺骨を土に還してあげたい方
遺骨を土に還してあげたい方は、納骨堂よりも一般墓や樹木葬のほうが向いています。
一般墓であれば、親戚間でタイミングを話し合って、納骨室の中にある遺骨を土に還すことができます。もう1つの樹木葬は、もともと自然に遺骨が土へと還る仕組みのお墓です。
納骨堂を選んだ場合にも、最終的には他人の遺骨とまとめて埋葬する「合葬」という形で土に還るものの、個別の土地に埋葬するものではありません。「遺骨を土に還すタイミングは家族・親戚で決めたい」「個別の土地で土に還してあげたい」という方は、納骨堂が向いていないと言えます。
墓石への愛着がある方
お墓に対する考え方は変わりつつあるものの、日本では今でもお墓というと墓石のイメージが根強くあります。墓石への愛着がある方は、納骨堂を選ぶと後悔につながる可能性があるでしょう。
墓石は購入費用が高く、維持費用や管理の手間もかかるという点がデメリットです。しかし、お墓参りのときに草むしりをしたり、墓石を水洗いしたりすると、祖霊との結び付きや家族の大切さを感じられるという方も多くいます。
墓石への愛着がある方は一般墓か、墓石型の納骨堂を選ぶとよいでしょう。
お墓参りで自然を感じたい方
従来の一般墓ではお墓が屋外にあるため、お墓参りは屋外で行われていました。しかし、お墓が屋内にある納骨堂の場合は、お墓参りも納骨施設の中で行います。風や太陽光が届かない環境でのお墓参りに違和感をおぼえる方は、納骨堂のお墓は合わない可能性が高いと言えます。
お墓参りで自然を感じたい方は、一般墓や樹木葬のお墓が合っているでしょう。
納骨堂が向いている方
納骨堂は一般墓よりも費用が安いため、お墓にかかる費用を抑えたい方には納骨堂がおすすめです。費用を抑えられる点の他にも、納骨堂が向いている方の特徴は3つあります。
最後に、納骨堂が向いている方の特徴を紹介します。
夫婦やお一人様・家族で利用したい方
納骨堂は基本的に費用を抑えられるプランを用意していて、夫婦やお一人様などの少人数利用に適しています。一般墓のように広い納骨室ではなく、夫婦2人や自分1人だけの遺骨を安置できるスペースがあればよい方は、納骨室の利用が向いているでしょう。
また、納骨堂の中には家族単位での利用に対応していて、遺骨の収骨スペースが広く取られている施設もあります。家族で利用したい方にも納骨堂はおすすめです。
お墓の跡継ぎがいない方
一般墓はお墓の永年利用を前提としていて、購入した区画・墓石は子どもや親族が跡継ぎとして管理継承する仕組みです。
しかし、もしもお墓を継いでくれる方がいない場合は、一般墓ではお墓を管理継承する方がいなくなって無縁仏になります。無縁仏になるとお墓の処分は墓地管理者に一任されることになり、墓石が撤去される可能性もあるでしょう。
納骨堂では永代供養を選択すれば、納骨堂の運営主体が遺骨の管理供養を行ってくれます。お墓の跡継ぎがいない方も、納骨堂であれば無縁仏になる心配がありません。
子どもや親戚に負担をかけたくない方
お墓の跡継ぎになってくれる子どもや親戚はいるものの、なるべく負担をかけたくないという方もいます。納骨堂は、子どもや親戚に負担をかけたくない方にも向いているお墓です。
納骨堂では、利用期間を決めて遺骨の個別安置ができて、子どもや親戚がお墓参りにやってくる場所を作れます。利用期間が終わった後は合祀される流れとなっているため、合祀への切り替えで子どもや親戚の手を煩わせることはありません。
近年は子どもや親戚にお墓のことで負担をかけたくない方が増えており、ニーズに対応できる納骨堂は人気が高まっています。
まとめ
納骨堂の費用は、納骨堂の種類や運営主体などによってさまざまです。一般的には納骨堂の種類ではロッカー型と位牌型、また運営主体では公営納骨堂の費用が安い傾向にあります。そのため、費用を安く抑えたい方は、それらの納骨堂を利用するのがおすすめです。
向島 たから陵苑は、参拝カード1枚で気軽にお墓参りができる自動搬送型の施設となっています。お備えいただくお花やお香は常時苑内にあるため、手ぶらでお越しいただけます。納骨堂をどこにするか検討中の方は、ぜひ資料で詳しい施設やプランの内容をご確認ください。